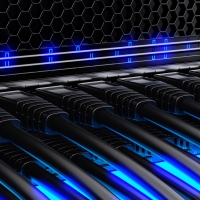- The best Chromebooks for students in 2025: Expert tested and reviewed
- The top-selling smartphone in 2025 so far might surprise you - here's why
- Apple Intelligence hasn't lived up to my expectations, but these 3 upgrades could win me back
- Samsung launches One UI 8 beta - what's new and how to join
- This 230-piece Craftsman toolset is still just $99 at Lowe's
3時間に1店舗がオープンするKFCの顧客改善レシピ:従業員体験とセットで取り組む

チャネルの増加、店舗の増加、顧客の期待の上昇に従業員がついていけない
フライドチキンの代名詞であるKFC、その創業は1952年に遡る。McDonald’sよりも3年前であり、世界で初めてフランチャイズを開始したのもKFCだ。現在、Yum!傘下のブランドとして展開しており、150カ国で3万店舗以上を構える。3時間おきに1店舗がオープンするなど、拡大を進めている。Yum!が発表した2025年第1四半期のグローバルの決算で、KFCの既存店売上高は前年同期比2%増となり、アナリスト予想の1.4%増を上回った。
KFCはこれまでにも、地域ごとに独自の顧客フィードバックを得る仕組みを導入していた。従業員調査は一部の国のみで、実施していない地域もあった。それらをグローバルで統一するという決断に至った理由はいくつかある。まずは各地域がバラバラの仕組みを導入していたため、地域による比較ができないという問題があった。次に、新店舗が次々とオープンする中で、KFCのカルチャーに基づく統一したブランド体験を顧客に提供することが難しくなっていた。南ア・ヨハネスブルグとタイ・バンコクとでフライドポテトの品質が違う、顧客サービスが異なることは、ファンの期待を裏切ることになる。
これらに加えて、顧客接点の増加がある。飲食業界に限らないが、ここ10年で顧客との接点が増えており、「それまでは、店舗での飲食、テイクアウト、ドライブスルーと3つだったチャネルが、現在はオンライン注文&店舗での受け取り、デリバリーサービス、ドライブスルーでの事前注文&ピックアップなどと増えている」と同社でゼネラルマネージャー兼COOのRob Swain氏は話す。
Swain氏が、顧客体験と従業員体験とをセットで取り組むと決めた背景には、自身のキャリアがある。ホスピタリティ業界で長くキャリアを積んできたSwain氏はトイレ掃除に始まり、あらゆることを経験したという。従業員の気持ちに寄り添うことなくして、顧客体験は改善しないと考えている。
「ゲスト(顧客)とチームメンバー(従業員)の間のバランスをとることが求められている。ゲストの体験への期待は年々上がっており、パーソナライズ、デジタル体験を求めている。これを満たすために、チームメンバーは数秒で意思決定をして正しい行動をとらなければならない。それにはデータが必要だ」(Swain氏)
このように市場の変化のスピードに合わせて自社の成長を支えるにあたって、地域ごとにバラバラのフィードバックを得ていては追いつけないーそこでグローバルで統一化することにした。「ビジネスのすべてのレベルで、データから洞察へ、洞察からアクション(行動)へとつながるシステムを構築したかった」とSwain氏。
顧客の声を従業員が行動に変える
そこで選んだのが、この分野で大手としてグローバル展開しているQualtricsだ。Qualtricsは体験管理「XM(Experience Management)」ブランドの下に、顧客向けの「XM for Customer Experience」と従業員向けの「XM for Employee Experience」などの包括的なソリューションを持つ。サーベイを行い、その結果を集計して分析し、改善に向けたアクションを提案することで、体験を改善できるというソリューションだ。ソーシャルメディアやレビューサイトなどから自社について何が話されているのかも把握できる。
「それまでのフィードバックは顧客の声を受け取るだけで、それを受けて従業員が改善に繋げることができていなかった。Qualtricsはその仕組みがある」とSwain氏。
Qualtricsを選んだ理由は上記のような技術だけではない。Swain氏はベンダーの選択基準を次のように説明する。「ベンダーはパートナー。我々が技術パートナーに求めていたことは、我々が求める優れた技術スタックがあり、将来も価値をもたらすロードマップがあること、そして信頼できるかどうか」。
パートナーという関係に納得するエピソードがある。導入にあたって、KFCはQualtricsの複数人の担当者に約4週間、2カ国の店舗に実際に入ってもらいスタッフのオペレーションを体験してもらったのだ。効果はあった。「Qualtricsの担当者は実際に体験するまで、クイックレストランでは時間をかけて洞察を得る時間がないということを実感していなかった」とSwain氏。
その日のシフトの中で、改善のためにやり方を変えるにはどうすればいいかと考える時間は多くて4-5分、そこで「アクションにつながる洞察をクイックにわかりやすく表示するツールとダッシュボードが必要」とKFCが求めるものを実現する形を詰めていくことができた。
そうやって構築したのが「KFC Listens」とダッシュボードだ。顧客と従業員には回答しやすいサーベイを用意した。ダッシュボードでは、店舗のマネージャーにPCを開く余裕はない。スマートフォンなどのモバイル端末で、視覚的にすぐに状況が把握できるものを用意した。
「単にテクノロジーを導入するのではなく、ゲスト(顧客)とチームメンバー(従業員)を中心にして、成長のペースを作る」とSwain氏は狙いを説明する。
KFC Listensは2022年に導入を開始した。まずは英国でスタートし、段階的に拡大している。現在7割近くをカバーしており、2024年秋より日本市場でも導入が始まっている。
話題製品のローンチ後、1時間でフィードバックを得て修正
KFC Listensの導入により、顧客からのフィードバック回収件数は300%増加した。Qualtricsの技術により、アンケートを配信するタイミング、質問の数や内容など回答のしやすさなどを工夫した結果だ。「ゲスト(顧客)をより細かく理解できるようになった」とSwain氏。また、ダッシュボードにより、役割に合わせた情報がすぐに得られる。Swain氏はCOOとして世界のどこで何が起きているのかをすぐに把握できるようになったという。
得られた効果の1つは、多面的な視点が得られるようになったこと。Swain氏はオーダー処理の精度を例にとって次のように説明する。間違った商品が届くという事象を解決する際、それまでは実行力にフォーカスしていたーーつまり、従業員に対して”間違えないように”などと声をかけるというものだ。しかし、 KFCには100万人の従業員がいる。「相手は人間、人間は間違いをするものだ」とSwain氏、幅広いデータを得ることで、従業員の実行力ではない視点を持つことができるようになった。
「メニューボードが複雑すぎるのではないか。店頭のキオスク端末のユーザーインターフェイスに課題があるのではないか。サプライチェーンに支障がありアイテムの変更を余儀なくされたため正確さに影響が出たのではないか」。メニューをもっと簡素化すると、顧客にどのような影響が出るのか。顧客と従業員の声を聞く仕組みを持つことで、マーケティング、テクノロジー、フランチャイジーがそれぞれの立場から協力して、オペレーションを改善するようになったという。
実際にインドでは、デリバリーの商品に対してケチャップなどの調味料が入っていないなどの漏れが多いことが顧客の声からわかった。そこで、注文伝票のレイアウトを改善して準備するスタッフが注文内容をすぐに理解できるようにしたり、アプリの注文状況追跡を調整して顧客が確認できるようにしたり、返金ルールの改善などを実施したという。それだけが理由ではないが、4ヶ月で顧客満足度は15%から52%に向上した。
データからアクションの例は他にもある。例えばオーストラリアでのデリバリー。ここ数年で定着した外部デリバリーサービスチャネルでは、注文が入った後どの段階で食事を作るのかを決定する独自のロジックがある。店舗やテイクアウトとは異なり、配送先がそれぞれ異なるので、準備のタイミングには注意が必要だ。早く作りすぎると鮮度が保たれず、遅く作ると間に合わない。またメニューによって準備に要する時間も異なる。そこで、KFCでは最適なタイミングで作る時間を計算するロジックを導入している。
従業員と顧客、両方のフィードバックを見たところ、従業員からは「ストレス増」、顧客からは「味と温度に課題がある」という声が多かった。そこで、技術チームがオペレーションチームと協業しながら注文と配達のアルゴリズムを調整し、顧客に最適な温度で届くように、従業員には余裕を持って準備できるようにした。これにより、ネガティブなフィードバックが減少したという。
また新メニューのローンチでもデータが活躍した。これまでは新しいメニューが導入されると、従業員のオペレーションが安定するまでに8週間を要し、問題があった場合はその把握に4-5週間が必要だった。店舗のマネージャーと話し合いの機会を持ち、顧客からの声を聞き、そしてデータを待つからだ。
これに対して、バンズを使わないスペシャルメニュー「Zinger Double Down」を英国でローンチする際、KFC Listenにより「発売初日の最初の1時間で声を収集できた」とSwain氏。すぐに、調理にあたるスタッフの作業を調整する必要があると判断し、48時間以内に新しいトレーニングプログラムを開始した。これにより、顧客の体験を損なうことなく話題メニューのローンチを成功させることができた。
組織をまたぐ取り組みに変える
このようにKFCの顧客と従業員体験への取り組みは軌道に乗り始めたが、そこに至るまでには苦労もあったようだ。難しかったことの1つが、さまざまな組織が一緒になって同じ問題の解決を進めること。何度も失敗をへていると振り返る。組織面では、顧客体験と従業員体験のチームを統合して同一リーダーの下で連携するようにした。また、部門を超えた委員会を立ち上げ、さまざまな立場の人とデータを元に語る文化を醸成していった。また、部門を超えたグローバル委員会を立ち上げ、XMの取り組みにおいてさまざまな立場の人の意見が反映される仕組みを設け、データを元に語る文化を醸成していった。
もう一つ工夫したことが、指標ありきではないこと。「それまでは顧客体験管理といえば顧客体験に関するKPIの改善を意味していたが、その場合、体験ではなくスコアの改善に焦点が当たり、本来の目的からずれる行動を従業員に奨励するということがあった」とXM担当インサイトと分析を担当するグローバルリードのAbby Czito氏はいう。例えば、顧客に提供するスピードに関する指標をあげようとすると、従業員への負担が増える。ストレスを感じている従業員がより良い顧客体験を提供できない可能性がある。KFC Listensでは顧客と従業員の両方のデータが得られることから、最前線にいる従業員がとった行動にフォーカスするように意識を変えていったという。
ビジネスへの効果はデータに表れている。最初にスタートした英国では、最高評価の顧客が1%増加するだけで、数十万回の追加来店と数百万ドルの潜在的な収益増加につながるという試算をはじいた。またデータから従業員体験と顧客体験の相関性も見えた。従業員体験が最も低い下位100店舗の顧客は、上位100店舗と比較すると「二度と来店しない」という確率が50%高いことがわかったのだ。
成果が出始めたところで、これからは予測やAIにも拡大したい、とSwain氏。「データは過去のもの。データから洞察を得て改善することは、バックミラーを見ながら車を運転しているようなものだ」(Swain氏)。
すでに予測アナリティクスやAIの模索を初めており、「まだ早期段階だが、顧客と従業員の声を聞き、パーソナライズされた体験を提供するというアプローチをさらに高速にできるし、問題が起こる前に対応することもできる」とSwain氏は期待を寄せる。
最後にSwain氏は、「一貫性とスケールを両立するためには、顧客と従業員の声を聞いてすぐに行動するーここにフォーカスしてスタートするべき」とKFCの顧客体験改善レシピを伝授する。「さまざまなタッチポイントからフィードバックを得て、チームがすぐに洞察を得られるようにすることで、従業員の行動を加速できる」(Swain氏)。