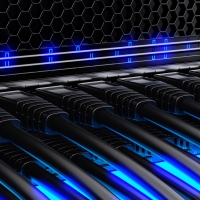- I tested a Pixel Tablet without any Google apps, and it's more private than even my iPad
- My search for the best MacBook docking station is over. This one can power it all
- This $500 Motorola proves you don't need to spend more on flagship phones
- Finally, budget wireless earbuds that I wouldn't mind putting my AirPods away for
- I replaced my Linux system with this $200 Windows mini PC - and it left me impressed
IT業界で最も誤用されている15の流行語

CIOは常に、技術的な専門用語をやめて “ビジネスの言葉 “で話す必要性について話している。しかし、彼らはビジネス部門が同じことをするのを拒んでいる。
財務、マーケティング、営業、オペレーションなど、他部門の同僚はかつてないほどデジタルリテラシーが高く、技術的にも精通しているというが、CIOが同僚に技術的な話がうまくなるよう迫ることはほとんどない。
ITの言葉が企業や社会そのものに広がっているにもかかわらず、IT部門の他の部署が、IT業界のツールやテクニックを表す略語やキャッチフレーズ、専門用語を学ぶことを求めることはない。
CIOをはじめとするITリーダーたちによれば、IT用語が企業や社会全体に広がっているにもかかわらず、その多くが何を言っているのか正確に理解できていないという。多くの従業員は、フレーズを使い回したり、用語を正しく理解できなかったり、専門用語を使いすぎたりしている。多くの場合、専門用語は本来の意味を失い始め、コミュニケーションやコラボレーション、時にはビジネスとITの整合性を崩してしまう。
CIO.comでは、長年にわたって技術系リーダーを対象に、誤用されることが多い用語を調査してきた。ここでは、現在最も誤用されているバズワードについて、リーダーたちの意見を紹介する。
1.デジタルトランスフォーメーション
「デジタルトランスフォーメーション」は、どの用語よりも多くのソースから引用され、このリストのトップに君臨し続けている。IT、あるいはビジネス全般において、ほぼすべての変化(大小を問わず)がトランスフォーメーション(変革)と呼ばれるようになったからだ。
「『デジタルトランスフォーメーション』は、漠然とした用語の1つでありながら、大規模なIT投資やIT/テクノロジー関連の履歴書に必ず記載されるほど、広く使われています。この言葉の意味を尋ねると、彼らはたいてい答えに窮する。もし答えが返ってきたとしても、それは一般的でハイレベルなものです」
では、バレットはこの言葉を定義しているのだろうか?
「このフレーズで重要なのは “トランスフォーメーション です」つまり、デジタルトランスフォーメーションの取り組みとは、新しいツール/プラットフォーム、新しいアプリケーションなど、テクノロジーを活用したものでなければなりません。」
彼はこう付け加える:「テクノロジー・リーダーとして、この言葉を耳にしたとき、私たちはこう問いかけるべきだ:1つは、実際のニーズとは何か?二つ目は、何を達成しようとしているのか?そして3つ目は、それをどのように達成するのか?これらの質問に答えることで、すべての利害関係者の理解が深まり、より良い情報に基づいた意思決定が可能になる。」
2.人工知能、機械学習、インテリジェンス全般
同率2位は、人工知能にまつわるすべての用語である:AI、機械学習、その他デジタル・インテリジェンスにまつわるあらゆるものだ。テクノロジー・リーダーたちは、これらの用語が実際に何を意味するのかについて一般的に混乱していると言う。
「誤解されているというのは軽く言っている。過剰に誇張されているというのが私の表現です」と、集合住宅資産管理会社ベル・パートナーズのIT担当上級副社長、アート・マッキャンは言う。
マッキャンによれば、現在、人々は「AI」を「自動化や基本的なアルゴリズムに関連するもの」を指す言葉として使っているという。
「そして、AIはあらゆるものに対する万能薬であり、ビジネスをより良くしてくれるという考えで使われている。しかし、真のAIの用途はもっと狭く、今日の(企業における)AIのほとんどは機械学習です」
彼は、様々なタイプのインテリジェンスの違いを説明することで、自身の組織内でこの用語の乱用や誤用に取り組もうとしている。「それが、私が社内で行おうとしている教育の一環なのです」と彼は言う。
3.戦略的
MITスローン経営大学院の上級講師であり、MITスローンCIOリーダーシップ賞のCIO賞共同委員長、米国議会図書館のデジタル戦略ラウンドテーブルのメンバーでもあるジョージ・ウェスターマン氏は、「戦略的」もこのリストに値すると言う。
ビジネス目標がある、特定の目的に向かって仕事をしている、CIOの場合はCEOに報告するというだけで、戦略的だと勘違いしている人がいる、と彼は言う。
「しかし、本当に戦略的であるならば、自分がどこに向かっているのかがわかっており、たとえ途中で方向転換をするとしても、そこに到達するための計画を持っているはずです」と、MITのグローバル・オポチュニティ・イニシアチブの創設者でもあるウェスターマンは付け加える。
4.アジャイルとDevOps
現代人はまた、自分たちがアジャイルだと思いたがる。しかし、ITチームがアジャイルであると語るとき、混乱が生じることがある。アジャイルであるというのは、適応性があるということなのだろうか?それとも、アジャイル手法に従ってソフトウェアを開発することなのだろうか?
ウィスコンシン大学ラクロス校の臨時CIOであるJim A. Jorstad氏は、人々が「アジャイル」をさまざまな概念に適用しているのを聞いたことがあると言う。
アジャイル」とは、柔軟性や適応性、変化への素早さだけを指す言葉ではない。アジャイル』は、それよりももっと具体的なものです。「アジャイルは仕事の方法論だが、それが何を意味するかはあまり知られていないと思う」
グローバルな調査・経営コンサルティング会社Everest GroupのパートナーであるYugal Joshi氏は、「DevOps」についても同様の現象が起きていると見ている。
「用語としての “DevOps “は、企業によって意味が異なります」とジョシ氏は説明する。「DevOpsはまさに、全員が開発と運用の両方をこなせる、全員がすべてをこなせるということです。開発者と運用担当者が別々になっているわけではありません。チームの全員が何でもでき、全員がカジタブルなのです。しかし、開発者と運用担当者が別々にいる1つのチームという意味で使われることもあります」
5.製品、プラットフォーム、アプリケーション、as-a-service
ジョシ氏は、「製品」と「プラットフォーム」という言葉も同様に、本来の定義を超えて誤って拡張されていると言う。
アジャイルとスクラムの世界における「製品」の定義は、ビジネスニーズを満たし、利害関係者に測定可能な価値を提供し、境界、顧客、利害関係者が明確なものである。
この定義は、一部のITショップでは通用するかもしれないが、ジョシ氏によれば、より一般的で日常的な意味での「プロダクト」とも融合し、ITからもたらされるあらゆる成果物を意味するようになったという。
「プラットフォーム」もかつてはもっと厳密な定義を持っていた、とジョシ氏は言う。
今では、多くのエンタープライズ・ベンダーやソフトウェア製品会社が、多くのアドオンを構築することで自社製品を『プラットフォーム』と呼ぶようになりましたが、私は今でもプラットフォームを一般的なサービス・セットだと考えています。IT部門は “プラットフォーム “の定義を多かれ少なかれそう考えている。しかし、IT部門の外ではそうではない。彼らは『CRMプラットフォームを導入したい』と言う。彼らは製品とプラットフォームを同じ意味で使っているのです」。
ジョシは、この傾向は「アプリケーション」という用語にまで影響を与えていると言う。
「マイクロサービスチームがアプリケーションを構築していると言うのを聞くかもしれないが、アプリケーションはエンドユーザーのためのものなので、技術的にはそうではない。アプリケーションはエンドユーザーのためのものだからです。そして今や『アプリケーション』は、ちょっとしたコードやサービスを意味することさえあるのです」と彼は言う。
経営コンサルティング会社Swingtideの社長兼CEOで、元CIOのダイアン・カーコ氏は、「as-a-service」という言葉もリストに加え、それが本来の意味ではなく、単なる製品やサービスに適用されるために誤用されていると指摘する。今、人々は食材のことを “as-a-service”と呼ぶ。
6.マイクロサービス
技術的なテーマに沿って、Data Conversion LaboratoryのCIOであるTammy Bilitzky氏も「マイクロサービス」をその例として挙げている。
「マイクロサービスとは、疎結合のサービス群を受け入れるアーキテクチャスタイルであり、各サービスはテストが容易で互いに独立し、最小限の機能しか公開しない。その代わり、1つ以上のウェブサービスの呼び出しを使用するあらゆるシステムを意味するようになりました」と彼女は言う。
7.エッジコンピューティング
人々を困惑させるもうひとつの専門用語がある。
HPの上級副社長兼HPSマネージド・ソリューションズ社長のジョン・ゴードン氏は言う。「単にクラウド上にないテクノロジーなのか?ネットワーク機器も含まれるのでしょうか?HPでは一般的に、エッジとはクラウドやデータセンターの外にあるコンピュート・パワーのことだと考えています。これには、PC、会議室機器、プリンターなどのデバイスが含まれますが、小売店の顧客分析や病院の音声ディクテーション・システムなども含まれます。エッジがユニークなのは、さまざまな物理的な場所に分散していることです。」
8.需要管理
CIOはどこの国でも長い要求のリストに直面し、最も重要なプロジェクトに優先順位をつけなければならない。しかし、他人の要求を管理するという考えは、このリストに載るほどの高い要求である。
「さまざまな利害関係者がいて、そのニーズは毎週のように変化している。この絶え間ない変化が、IT部門に対する絶え間ない要求を生み出している。IT部門が需要を管理できるという考え方は誤りです。IT部門が管理できるのは、単にキャパシティだけです」と、エル・リオ・ヘルスのCIO、スーザン・スネデーカー氏は言う。
9.帯域幅
「帯域幅」という言葉も、その誤用が多いことから、ここに一票を投じたい。多くの技術者が知っているように、この言葉には非常に技術的な意味がある。しかし現在では、利用可能な時間への言及として誤って使用されている。
「それはスピードと容量のことだ。利用可能な時間のことではありません」とジョルスタッドは抗議する。「気が散る言葉だ。だから、言いたいことを言えばいいんだ:この仕事をする時間がないんだ」
10.ノーコード/ノーIT
何人かのCIOは、これらの言葉を誤用として挙げ、第一に、すべてのソフトウェアにはコードがあること(たとえユーザーがコードを書かなくても軽いプログラミングができるとしても)、第二に、企業向けソフトウェアの導入には依然としてIT部門の作業が必要であることを指摘した。
「これは、私が目にする最も嫌なバズフレーズのひとつであり、誤用でもある。ソリューション・ベンダーのウェブサイトで “IT部門不要”と謳っているのを読むと、いつも腹が立ちます」とスネデーカー氏は言う。
「”IT部門不要”という宣伝文句は、組織やエンドユーザーを誤解させ、潜在的に危険なシャドーITの道を作り出します」とスネデーカーは説明する。「ベンダーのソリューションはIT部門の関与を必要としないかもしれませんが、ソリューションのセキュリティ評価(特に規制業界の組織)、ユーザーの適切なプロビジョニング、企業データの安全性の確保からデータの本国送還まで、常にIT部門の関与が必要です」
彼女はこう付け加える:「IT部門は、組織のリーダーシップによって承認されたITソリューションを、会社の業務遂行に使用することを促進するパートナーとして、常にそのテーブルにつくべきです」
11.技術的負債
カーコ氏は、IT部門の内外を問わず、人によって異なる意味を持つ言葉として「技術的負債」を挙げている。
“技術的負債 “はよく使われるが、誤解されることも多い。「技術的負債という言葉はよく使われますが、誤解されがちです。誰もが知っておくべきことだと思っている。
ある人は、問題のあるコードを、チームが後で修正することを理解した上で、スピードのために故意にデプロイしたものと定義する。また、レガシーシステムやその保守コストを指す言葉として使う人もいる。
Carco氏は、IT予算を増やすために、この言葉の曖昧さ、財務的な必要性を利用するCIOを何人か見てきた。この言葉には “負債 “という意味が含まれているため、”負債 “は自分が負っているものであり、自分にはどうすることもできないという意識があるのです」とカーコ氏は付け加える。
この言葉についてコンセンサスが得られるといいのだが。カーコは、ChatGPTとGoogle検索を使って、他の人たちがどのように定義しているかを調べたが、「定義にまったく同意できない」ことがわかったという。
12.データ用語
データウェアハウス、データレイク、データファブリック、データマイニング、ビッグデータなどなど。そして、AIと同様、データの世界はあらゆる問題に対する救済策として宣伝されている。
マッキャンは、そうした要素が働いている例として、「ビッグデータ」という言葉の使い方を指摘する。多くの人々は “ビッグデータ “を単に大量のデータという意味でとらえており、データの量こそが解決策であるかのようにほのめかしているが、それは現実離れしている。
「ビッグデータは誇張されすぎており、データが多ければ多いほど良いというように扱われる一方で、データの質、データの出所、データが正しく入力されているかどうかは無視されている」とマッキャンは言う。「現実には、データを管理する適切なツールがなければ、データは単なるノイズの束に過ぎず、ビジネスに必要なものを与えてはくれない。」
13.データ漏洩
データというテーマにこだわって、LaserficheのCIOでSociety for Information Management(SIM)研究所の諮問委員会のメンバーであるトーマス・フェルプス4世は、「データ侵害」をもう一つの問題用語として挙げている。
「『AI』や『デジタルトランスフォーメーション』といった用語とともに、『データ侵害』という用語も誤った文脈で誤用され、重大な影響を及ぼす可能性があります。サイバーセキュリティでは、”セキュリティイベント”、”インシデント”、”侵害 “といった用語がよく使われます。セキュリティ・イベントとは、ユーザーのログオンやファイルのダウンロードなど、セキュリティに影響を及ぼす可能性のあるサービス、システム、ネットワークで発生するあらゆるタイプの事象を指します。それ自体は、悪意があったり、ポリシー違反であったり、法的な意味を持ったりしないかもしれません。」
「セキュリティ・インシデントとは、システムの機密性、完全性、または可用性に悪影響を及ぼす可能性のある、異常と思われる事象または一連の事象のことです。危殆化の兆候や、調査を必要とするセキュリティ・ポリシー違反があるかもしれない。セキュリティ・インシデントは、それ自体ではデータ侵害ではありません。違反とは、規制対象データの損失、システムの危殆化、または不正な開示があった場合を指しますが、これは重大な法的意味を持ち、さまざまな法律、規制、さらには特定のビジネス契約によって定義されます。これには、GDPR、HIPAA、CCPA、その他の規制要件に加え、最近のSECのサイバーセキュリティ開示規則が含まれます。」
意味論は重要だとフェルプス氏は言う。「最近、ある大手エンドポイント・セキュリティ・ソリューションのソフトウェア・アップデートで起きた事件を見ると、その事件はコンテンツ・アップデートの事件であり、セキュリティ侵害ではありませんでした。多くのソフトウェア契約には、セキュリティ侵害やデータ侵害に特別に適用される条項や契約上の救済措置があります。法務部門がセキュリティ侵害の特定に関与していない限り、IT担当者はいかなる状況においても『データ侵害』という言葉を使うべきではありません」と同氏は説明する。
14.マルチクラウド
同じようなことで、ITエグゼクティブのケン・ピディントン氏も「マルチクラウド」の誤用を指摘している。彼が「最も正しい定義」と呼ぶ、「異なるクラウドプロバイダーやサービスの複数のクラウドコンポーネントで1つのシステムを設計した場合」を指す。
しかし、多くの人はマルチクラウドとは、クラウドベンダーやSaaS(Software-as-a-Service)が混在する企業を指すと考えている。
「しかし、多くの人はマルチクラウドがクラウドベンダーとSaaSの混在した企業を表していると考えている。私は、この間違った使い方が世界の終わりとは思わないが、いつも悩まされる。しかし、それを理解すれば、その課題とそれを目指す理由について、より良い会話ができるようになる」
15.メタなあらゆるもの
このカテゴリーに分類される用語、技術、概念はたくさんある。メタバース、ブロックチェーン、暗号、デジタルツイン、NFTなどだ。TEKsystemsのCTOであるラム・パラニアッパンが説明するように、メタバースとは「仮想世界に等価なものを作り出すこと」であるが、彼や他の人々は、多くの人々がまだこの考えを理解するのに苦労していると言う。